さて、前回の続きで、私なりの4局面プラスαです。
読めばわかりますが、意外と当たり前のことなんです。
でも、こうしたことを言語化しておくと、実際のゲームでうまくいっていない場面を分析しやすくなります。
こうした現象が起きてるのは、その前のこの局面に問題がありそうだな。
今は、相手のミスで失点にはなっていないが、このままでは失点しそうだから、この局面はもっと細かな修正が必要そうだな
…など。ミスの原因を認知しやすくなります。根性論で解決しないためにも、理論武装していきましょう(^^)
そして、それ以降の私なりの局面の定義を今回はご紹介します。まだまだ、発展途上の部分ですから、随時追記していくかなぁと思いますが、とりあえず、ここまでの部分を書いていきます。
注:あくまでも私の個人的な定義づけです。年齢、その他状況によってはマッチしないこともありますのでご注意ください。なお、まだ未完成な部分もありますし、常にプレーモデルは変化するものと考えているため、今後加筆、訂正もありえます。
4局面プラスα ー6 「pre -transition (攻→守)」のphase ー
【pre-transition(守→攻)の定義】
まだ自チームがボールをかろうじて保持しているが、状況によってほぼこの後失うであろう状況。4局面の「守→攻」に移る直前の段階。
サッカーを経験した人なら分かっていただけると思いますが、
「あー、これ失いそうだなぁ。」「そんなスピードでドリブルで突っ込んだら、失いそうだ」
とか思うことありますよね?
その瞬間にすでに、攻→守のフェーズの準備をしておくんです。
最悪まだ、行動に出来なくてもいいです。
「失いそうだ」と意識しておき、次の危険な状況を認知しておく、
できれば、コーチング、アクションを始めておけるといいですね。
失ってから、動き始めるのでは後手になります。だから、あらかじめ危険な状況を認知しておくことはとても重要だと考えてています。
普段から、リスクマネジメントを指導しているコーチもたくさんいらっしゃいますが、これも
いつ、何を(誰を)、どうするか、ということまで言語化させておくことで、瞬時の判断がスムーズになっていきます。
これも一種の戦術メモリーですかね。
ですので、このいわゆる4局面の間の局面も切り取って、考えるようにしています。
皆さんはいかがですか?
4局面プラスα ー7「pre -transition (守→攻)」のphase ー
【pretransition(守→攻)の定義】
まだ自チームがボールをかろうじて保持しているが、状況によってほぼこの後相手チームが奪うことが予想される場面。4局面の「攻→守」に移る前の直前の段階。
これは、前述の6局面目の反対のじょうきょうですね。
おなじです。マイボールになりそうだな。ってやつですね。
数的状況を見ると、今は相手ボールだけど相手チームのあの選手ならボールを奪えそうだな。とかですね。
これも、準備しておくと、攻撃がスムーズに進みます。カウンターの切れ味も増しますね。
カウンターのカウンターって、めっちゃチャンスですよね。だから、このPre シリーズはかなり重要な局面だと思っています。
いままで「感」「センス」ですませていたものを言語化することは大切ですよね。







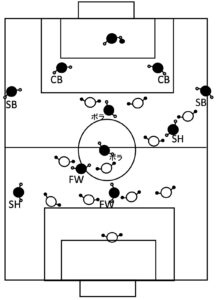

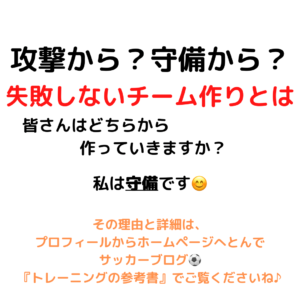
コメント